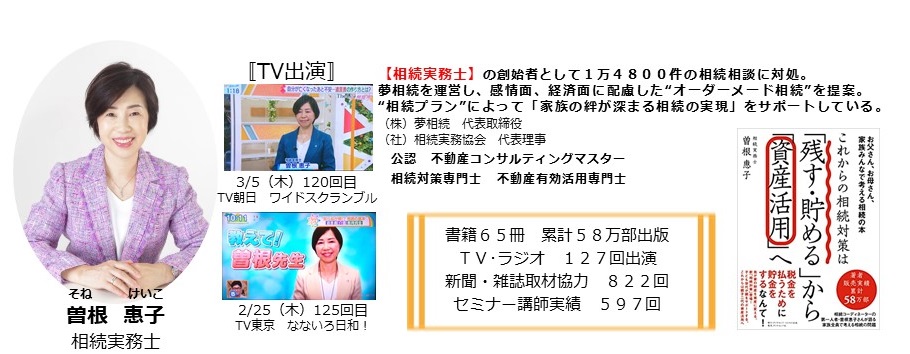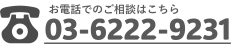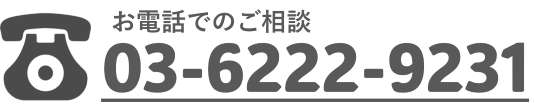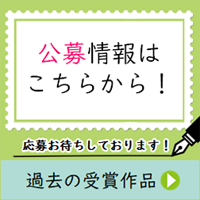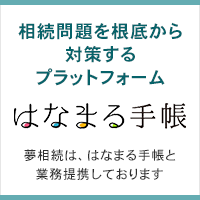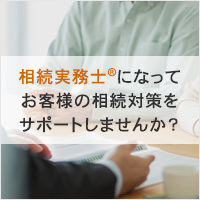事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
子どもがいない二人暮らしで起きた突然の相続 ――「支える人」がいなければ、相続も暮らしも立ち行かない

■兄嫁の突然死 くも膜下出血
60代のTさん(男性)が相談に来られました。Tさんは次男で、70代の兄(長男)と2人きょうだいです。兄は大学を出て仕事をするようになってから実家を離れましたので、次男のTさんが両親と同居して、現在も実家を相続して、妻と娘の3人で生活しています。
兄は理系で上場企業の研究職に就いたのち、国立大学の教授を歴任し、70歳まで教鞭を取っていました。大学の近くに家を買って夫婦2人暮らしをしてきています。
兄夫婦には子どもがいませんので、いつも夫婦で仲良く生活しているというイメージを持っていたとTさんはいいます。
そのはずが、今年の年明け早々に、義姉の兄、ご長男から突然電話があり、「妹が亡くなっていた」と知らされたのです。夫であるTさんの兄からは何の連絡も来ていないため、全く寝耳に水、驚いたと言います。
ご長男が言われるには、「妹は自宅の玄関で倒れているところを警察に発見されました。連絡が取れないことを不審に思ってケアマネジャーに連絡を取り、警察を呼びました。死因はくも膜下出血で、死後数日経ってからでした。」と。
義姉の発見が遅れたのは、兄自身が妻の異変に気づけなかったからというのです。衝撃的だったのは、認知症が進行している兄が、倒れた妻を見てもそれを妻と思わずだれかよその人と思って対応できなかったようです。
Tさんにとって自慢の兄で、いつでも理路整然と話をするタイプで、まわりの人々も一目置いています。大学を70歳でリタイアし、少し認知気味だと兄嫁から聞いてはいましたが、頻繁に会うこともなかったため、要介護1になったとは聞いていましたが、そんな状態だとは想像もしていなかったといいます。
■突然の相続 遺産分割協議書が必要
兄はかなり混乱していたようで、すぐにショートステイ施設へ一時的に移されましたが、現在では落ち着いていて会話もできるように回復しているといいます。
義姉は70歳になったばかりで、しかも突然死。遺言書はありませんでした。子どもがいないため、義姉の相続人は配偶者の兄と義姉の兄2人。基礎控除は4800万円です。
義姉はきちんとした人で自分で財産をまとめたエンディングノートがあり、銀行と証券会社の取引先は確認ができました。不動産は兄と共有の自宅です。評価をすると自宅の持ち分が1000万円、預金2000万円、株5000万円で合わせて8000万円程度だと想定されましたので、相続税の申告が必要とわかり、当社でサポートしながら税理士と申告の準備を進めています。
義姉の兄二人は妹が親から相続した株の一部をもらいたということで、法定割合を基準として遺産分割協議をすることになりました。預金や株の解約手続きは義姉の兄が動くということで、遺産分割協議書は出来上がり、義兄が解約を進めています。
■施設入所と信託・後見制度の選択
兄は一時の混乱からはかなり回復し、普通に会話もできますが、けれども義姉がいなくなっての家でひとり暮らしはできそうにありません。そもそもが、家事は専業主婦の義姉が担当してきましたので、兄には自分で食事の用意をしたり、家の掃除をしたりする発想がなかったのかもしれません。
よって、兄とTさん家族と話し合ってTさんの家から20分程度のところにある高齢者住宅に住み替えてもらうようにしました。あわせて、いよいよ兄の認知が進んだ時のために、Tさんと任意後見契約を締結することをお勧めしました。財産がTさんに集まるのを避けるためにもTさんの妻にも遺贈する遺言書を作成することもお勧めし、ほどなく両方とも出来上がります。
■二人暮らしだからこそ、備えておくべき
今回の一件で、子どもがいないご夫婦の二人暮らしでも、「リスクが高い」ということを感じます。配偶者のどちらかに何かあったとき、その後の生活を支える人がいない。本人たちが元気なうちに遺言書を作っておくべきだったし、万が一に備えて財産の所在や名義などを「見える化」しておく必要がありました。
Tさんの兄も兄嫁も、教養ある穏やかな夫婦でした。きっと老後もお互いに支え合って過ごしていけると信じていたはずです。
ですが、その支えが突然消えたとき、いかに準備不足が命取りになるかを、Tさんは目の当たりにしたといいます。
■子どもがいないなら、「第三者の支援」を前提に
今、多くの高齢者が「夫婦ふたりで老後を迎える」ことを前提に生活をしています。でも、その「ふたり」は、どちらかが倒れたら終わりです。特に子どものいない世帯では、親族の中に支援者がいなければ、その後の暮らしが一気に立ち行かなくなります。
「うちは関係ない」と思わずに、早い段階で信託契約や遺言の作成をしておくことが、いまの時代、大人としての責任ある選択肢なのだと強く感じました。
Tさんの兄のように、認知機能がまだ一部保たれているうちなら、遺言も、任意後見契約も、信託契約も可能です。準備さえしておけば、本人の望む暮らしを実現してあげられるのです。
家族の数だけ相続の形があります。けれども「自分がいなくなった後、大切な人に迷惑をかけたくない」という想いは、誰にとっても共通の願いではないでしょうか。
これからの時代は、「夫婦ふたりで完結する時代」ではなく、「第三者を含めた支え合いの仕組み」が必要です。
■今回の相続で見えた教訓とリスク
【問題点1】夫婦ふたり暮らしの限界
どちらかが倒れたとき、助けを呼ぶ人がいないのが最大のリスクです。特に認知症を抱える場合、救急対応ができず、死亡後の発見すら遅れることになります。
【問題点2】財産の不透明さ
相続が発生しても、どこに何があるかわからない状況では、財産管理も分割も困難です。夫婦間の財産の区別も不明確であることが、手続きを一層複雑にしています。
【問題点3】意思能力が残っている間の準備不足
後見制度を避けたい場合、信託や遺言を早めに準備することがカギになります。
今回、意思能力が一部残っているからこそ信託に移行できましたが、タイミングを逃していたら法定後見に移行するしかなかった可能性があります。
■まとめ――「第三者支援」を前提にした老後設計を
子どもがいない夫婦にとって、老後・介護・相続のすべてが「自己完結できないリスク」を示す典型例です。
特に以下の3点は、今後の相続支援の現場で多発するであろうと予測されます。
- 配偶者の急逝 → 認知症の本人が残される
- 誰も財産の管理ができない(後見人か信託が必要)
- 財産の全容が不明で、手続きも煩雑
今後の高齢化社会では、「夫婦ふたりで完結する暮らし」はもはや幻想です。
家族以外の支援者(相続実務士や信託専門家)といかに早期に連携するかがカギになります。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆