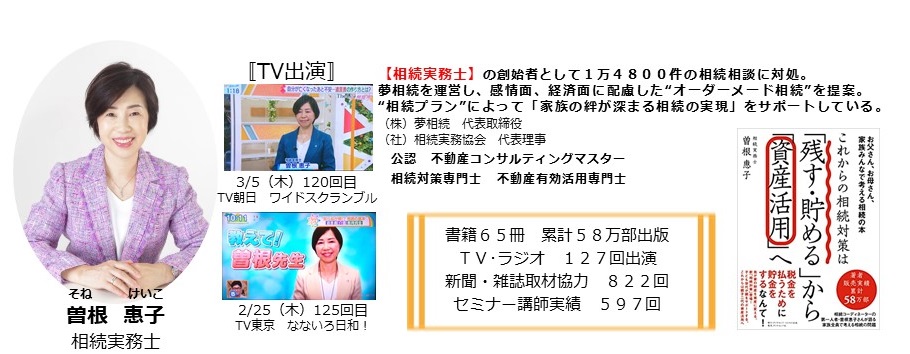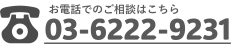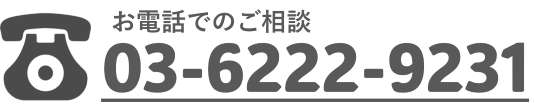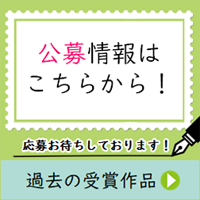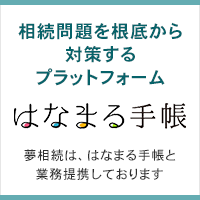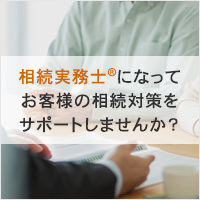事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
海外在住でも日本国籍があれば住民票、印鑑登録できて遺産分割協議が楽に!

■海外生活が長かった
Hさん姉妹(40代)が、相談に来られました。Hさんの父親(80代)が亡くなったため、相続の手続きが必要となったのですが、相談に来られたのは葬儀が終わった翌日です。
一般的には相続の手続きをするのは四十九日が過ぎてからのことが多いのですが、Hさん姉妹にはある事情がありました。
それはHさん姉妹は普段は日本ではなく、ヨーロッパのとある国で生活しており、生まれてから日本に住んだことはないということなのです。
父親が亡くなったという知らせを受けてHさんと妹は葬儀のために来日したのでした。
父親はもとは商社勤務で、Hさんが生まれた国の駐在員として仕事をしており、母親と出会って結婚したといいます。現在は離婚していますので、父親と相続人はHさんと妹の2人です。
■リタイヤ後は日本で
父親は七十歳まで仕事をしていましたが、リタイヤし、離婚もして一人暮らしになりましたので、老後は日本で生活したいと15年ほど前に帰国し、自宅のマンションも買って生活していました。Hさん今井も何度も父親の家に訪れたことはあります。
80代になったものの、父親は至って元気で自宅のマンションで生活して、友人と交流したり、旅行に出かけたりしていました。
ところが昨年、急に体調を崩して入院。検査の結果は余命宣告される病気が見つかったと言います。Hさん姉妹も病院に駆けつけましたが、ほどなく落ち着いて日常の生活に戻れたこともあり、Hさん姉妹も自分たちの国に帰っていましたが、先月急変、帰らぬ人になってしまったのでした。その間、相続に関する準備はほとんどできずだったと言います。
相続の手続きのサポートをしてもらいたいということで当社でコーディネートを引き受けました。
■日本に住所がないと登録できない
日本に住所がない(=住民登録がない)子どもは、日本の市区町村で住民登録も実印登録も原則できません。理由と対応策はつぎのとおりです。
◇住民登録(住民票)について
原則:日本国内に住所(居住実態)がないと住民登録はできない
住民基本台帳法に基づき、住民票は「日本国内に生活の本拠がある者」に作成されます。海外在住の日本国籍者は「在留届」を在外公館に提出し、日本には住民票がない状態になります。よって、日本に一時的に来日しただけでは、住民登録(住民票の作成)はできません。
◇実印登録(印鑑登録)について
原則:実印登録は「住民票のある自治体」に限る
印鑑登録制度は住民票のある人だけが利用できます。住民票がなければ、実印登録をすることも、印鑑証明を取得することもできません。
■海外在住の相続人は「印鑑証明に代わる書類」で対応
日本に住民票がなく、実印登録もできない相続人については、以下のような方法で対応します:
【署名証明書】+【サイン証明】
日本大使館・領事館で取得可能 本人確認のうえで、署名証明書を発行してもらえます(印鑑証明の代用)
【宣誓供述書(Affidavit)】などを併用することもあり
◇相続登記や預金解約ではどうする?
|
手続き内容 |
実印必要? |
海外在住相続人の対応 |
|
相続登記 |
実印+印鑑証明 |
→ 日本の印鑑証明がなければ、大使館発行の署名証明書で代用 |
|
預金解約 |
金融機関による |
→ 実印がない場合、署名証明や宣誓書で代替可(金融機関に要確認) |
■父親の家があることで手続きが楽に
Hさん姉妹は日本国籍があり、日本に父親の自宅があったことから、相談に来られた翌日、父親の自宅住所に住民票登録をし、実印登録もし、住民票、印鑑証明書を取得することができました。
父親の財産は自宅マンションと預金、株、車などで8000万円程度ですが、相続税の申告、納税が必要になります。父親は遺言書を作成していなかったため、遺産分割協議書が必要ですので、2回目に来て頂いたときに遺産分割協議書を作成し、署名、調印を済ませて、出来上がりました。
預金、株の解約や自宅マンションと車の名義替えは、司法書士には依頼するとして、司法書士への委任状も作成、まずは車の名義替えから手続きをしてもらいました。自宅マンションはしばらく維持するということですが、車は駐車料金がかかり、日本で乗ることはないということで、早めに売却したいということです。
【父親の家に住民登録できるケース】
|
状況 |
登録できるか |
解説 |
|
父の家に実際に住む |
◎ 可能 |
帰国し、実際にそこに居住するまたは
|
|
相続のための一時帰国のみ |
△ ケースによる |
滞在が短期(数日~1週間など)の場合、
|
|
住まずに書類上の住所だけ登録したい |
✕ 原則不可 |
居住実態がないと虚偽の届出となり、
|
【手続き方法】
- 転入届(住民異動届)を市区町村に提出
- パスポート、戸籍、在留証明などで本人確認
- 居住の実態を説明(場合によっては現地確認される)
【補足】こんなケースではどうなる?
|
ケース |
ポイント |
|
相続や不動産登記のために住所が必要 |
短期滞在なら無理に住民登録せず、
|
|
長期間日本に滞在する予定(数ヶ月以上) |
生活拠点とする意思があれば、
|
|
相続で父の家を取得したあと住む予定 |
実際に住めば、当然住民登録は可能です
|
【結論】
|
質問 |
回答 |
|
父の家に住民登録できるか? |
✅ 実際に住む意思・実態があれば可能 |
|
一時帰国や短期滞在のみの場合 |
❌ 原則不可(居住実態が必要) |
■まとめ
Hさん姉妹が来られて最初に確認したところ、海外在住ということで、住民登録、実印登録もないということでした。日本語もほとんど話さず、普段は母国語が主。相談に来られた時は商社勤務時代からの父親の友人が同行されていました。その方は海外勤務時代からの友人でHさんの住む国に勤務していたことから子ども時代から二人と交流があり、信頼関係があります。父親が日本に帰ってからも交流は続いていて、「万が一の時は娘たちをサポートして手続きを頼む」と言われていたそうです。英語で2人に通訳しながらの手続きを進められましたのでした。
Hさん姉妹は日本の苗字と名前の漢字の登録がありますので、遺産分割協議書や司法書士への委任状には日本名で署名し、実印を押印されていましたが、書き慣れない日本名に苦戦しながらも出来上がりましたので、その後すぐに車の名義変更、次に預金、株の解約、自宅マンションの相続登記を進めることができました。
相続税の申告は路線価が発表されてからになるため、すこし先になりますが、司法書士の方で残高証明書を取得して、進めることになっています。
相談に来られてから遺産分割協議書ができるまで数日ほど。手続きが滞りなくできることがわかり、Hさん姉妹は少しひと段落として、葬儀のために来日していた時から2週間程度で母国に帰国でき、落ち着きましたと連絡がきました。
残るは相続税の申告ですが、期限までまだ8ヶ月以上あります。それでも路線価が発表されると申告はできるため、早めに済ませていく予定です。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆