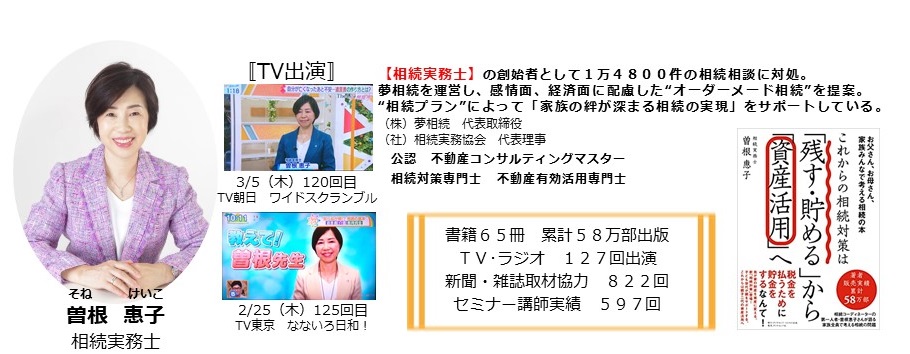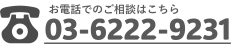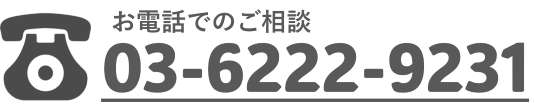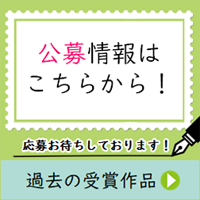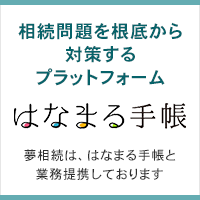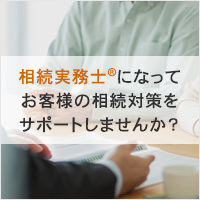事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
財産5億円。等分のはずが遺言書で自宅土地のみ5%。理不尽な結末。

■「お父さんは、私を信じてくれていたはず」
Bさん(仮名・70代)が父親の相続のことで相談があると来られました。
数年前、父親と同居する長女である姉が亡くなり、それからは近くに住むBさんが父親の介護を担当してきたといいます。
高齢の父は持病があり、入院・通院を繰り返す生活。買い物、家事、通院の付き添い、介護保険の申請──すべてをBさんが担ってきました。
父は土地持ちで、賃貸アパートや駐車場などの不動産を複数所有。その総額は約8億円、借入金を差し引いた正味の財産は約5億円にのぼります。
■生前の遺言は「ほぼ等分」
まだ長女が存命の頃、父は遺言書を作成していました。内容は、長女と次女であるBさんがほぼ等分に財産を分け合うという、公平なものでした。遺言書を作るときには姉とBさんが父親を公証役場に連れて行きましたので、状況は分かっています。
遺言書には姉やBさんが父親よりも先に亡くなっている場合は、その子どもたち(孫)が相続するとして予備的な内容も盛り込まれていましたので、姉が亡くなったとしても特に作り直しをしてなくてという発想にはならなかったと言います。
■父の死後、届いた“別の遺言書”
父が亡くなったのは、二カ月前。葬儀や手続きに追われ、少し落ち着き始めた頃──Bさんのもとに見知らぬ司法書士から封筒が届いたのです。すると、そこには新たな遺言書が。
『次女Bには、次女の自宅土地のみを相続させる。他の財産は、亡長女の長男・二男に相続させる。』
あまりの内容に、Bさんは手が震えました。
「これは父の意思なのか……? 本当に理解して書いたのだろうか……?」
■財産5億円、次女の取り分は自宅土地だけ
新しい遺言書によって、Bさんが相続できるのは自宅の土地(評価額1,980万円)のみ。現金も収益不動産も、一切なし。賃貸物件の収益は全て甥2人のものとなります。
■法定相続分ならこうだった
もし法律どおりの相続(法定相続分)で分けていれば、こうなります。
- Bさん(次女):1/2 → 約2億5,000万円(本来)
- 甥(長女の長男):1/4 → 約1億2,500万円
- 甥(長女の二男):1/4 → 約1億2,500万円
※本事例の設定上、実際の税額計算は4億円ベース(借入控除後)で行います。
相続税の試算(参考)
では、与えられた条件で順番に計算していきます。
今回の試算は財産総額を「正味5億円」として行います。
- 課税対象額
基礎控除は
3,000万円 + (600万円 × 法定相続人3人) = 4,800万円
課税価格合計は
5億円 − 4,800万円 = 4億5,200万円
- 法定相続分ごとの課税価格
- Bさん(1/2)
- 4億5,200万円 × 1/2 = 2億2,600万円
- 甥(長男)(1/4)
- 4億5,200万円 × 1/4 = 1億1,300万円
- 甥(二男)(1/4)
- 4億5,200万円 × 1/4 = 1億1,300万円
- 各人の相続税(速算表で計算)
2025年現在の相続税速算表(抜粋):
- ~1,000万円:10%(控除0)
- ~3,000万円:15%(控除50万円)
- ~5,000万円:20%(控除200万円)
- ~1億円:30%(控除700万円)
- ~2億円:40%(控除1,700万円)
- 2億円超~3億円:45%(控除2,700万円)
- 3億円超~6億円:50%(控除4,200万円)
- 6億円超:55%(控除7,200万円)
- Bさん(課税価格 2億2,600万円)
該当区分:2億円超~3億円(税率45%、控除2,700万円)
- 2億2,600万円 × 45% = 1億170万円
- 1億170万円 − 2,700万円 = 7,470万円
- 甥(長男)(課税価格 1億1,300万円)
該当区分:1億円超~2億円(税率40%、控除1,700万円)
- 1億1,300万円 × 40% = 4,520万円
- 4,520万円 − 1,700万円 = 2,820万円
- 甥(二男)(同じく 1億1,300万円)
同計算で 2,820万円
- 相続税総額(法定相続分)
7,470万円(Bさん) + 2,820万円 + 2,820万円
= 1億3,110万円
- 実際にBさんが5%しか相続しない場合の税額
財産総額の5%は
5億円 × 0.05 = 2,500万円(取得額)
相続税は、総額1億3,110万円を相続割合で按分します。
1億3,110万円 × 0.05 = 655万5,000円
✅ 計算結果まとめ
- 法定相続分での総相続税額:1億3,110万円
Bさんが5%取得時の相続税:約656万円
■自分のお金で納税する理不尽
遺言書の内容どおりに相続すれば、Bさんの自宅の土地は自分の名義にできます。しかし、それは決して喜べる話ではありません。なぜなら、その土地には評価額に応じた相続税が課され、計算すると656万円。
ところが、Bさんは現金や預貯金を一切相続しないのです。つまり、税金を払うための資金は1円も受け取れません。相続税の納付期限は亡くなってから10か月以内。猶予も待ってはくれません。結局、Bさんは自分の貯金や生活資金を切り崩し、「もらったもの」に対して自腹で税金を納めるという本末転倒な状況に追い込まれるのです。
家を守るために父を看取り、介護を担い続けた結果、残ったのは土地だけ。そしてその土地は売らない限り現金化できず、固定資産税や維持費も毎年かかります。「財産を相続した」というより「負担を背負わされた」と言ったほうが、Bさんの心境には近いでしょう。
遺言書の内容どおりに相続すれば、Bさんの自宅の土地は自分の名義にできますが、そのための相続税は656万円。現金は一切相続しないわけですから、相続税は自分のお金を出して払わなければならないのです。
■法律上の救済策はあるが…
相続実務士として真っ先に思い浮かぶのは、遺留分侵害額請求です。
Bさんの遺留分は、法定相続分(1/2)のさらに1/2、つまり1/4(1億円相当)。
実際の取得額との差額を、甥たちに金銭で請求できます。
また、長年の介護があれば寄与分を主張し、相続分を上乗せできる可能性もあります。
しかしどちらも、証拠資料や時間、精神的負担が大きく、Bさんは「もう争いたくない」と法的手段を断念しました。
■繰り返される「介護した人が損をする相続」
このケースは珍しい話ではありません。
遺言書の内容ひとつで、何年も介護を続けた相続人が、現金ゼロ・納税だけ負う結果になる──現場では何度も目にしてきました。
■防ぐための3つの備え
- 遺言は専門家と作る
作成過程で全員が納得できる内容にし、後日のトラブルを防ぐ。 - 介護の記録を残す
日記、領収書、通院記録などが寄与分の証拠になる。 - 納税資金の確保
生命保険や生前贈与で“現金なき納税”を避ける。
最後に
「父は、本当は私にもっと渡したかったと思う。でも、この遺言がある以上……」
Bさんの声は静かでしたが、その胸の内は複雑です。
相続は、家族の人生の最終章です。
しかし準備を怠れば、思いもよらぬ結末を迎えます。
夢相続では、こうした理不尽を防ぐため、生前からの相続設計と納税対策を一貫して支援しています。
介護した人が報われる相続を──
それが、私たち相続実務士の願いです。
■この悲劇を防ぐために
この事例は決して特別ではありません。
遺言が一方的に作られた場合、相続人同士の関係悪化や、不公平感による争いは避けられません。特に、介護を担った相続人が不利な扱いを受けるケースは後を絶ちません。
防ぐためには、
- 遺言作成の段階から全相続人が納得できる説明を受ける
- 介護の記録を日記や領収書で残しておく
- 生前から専門家を交えて財産分割や税負担の試算を行うことが必要です。
🔶 無料相談を是非をご利用ください
相続実務士®が、ご家族の立場に立ってサポートします。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆