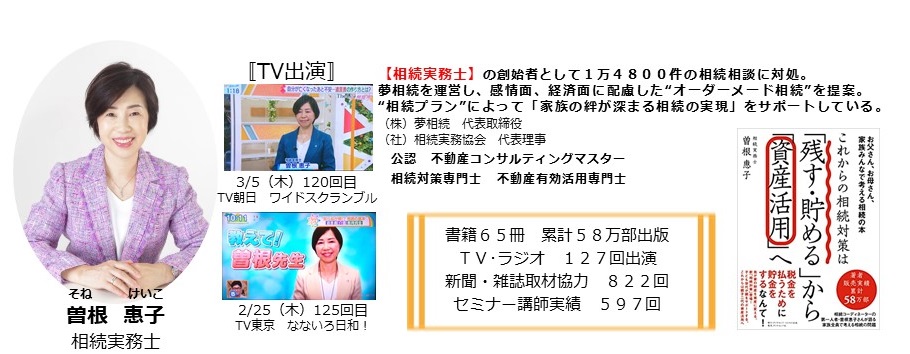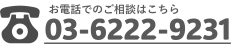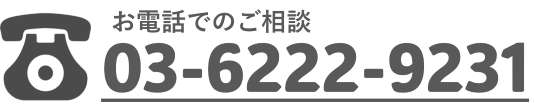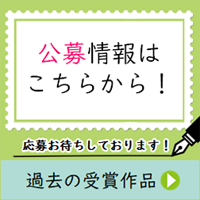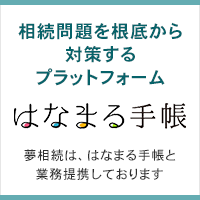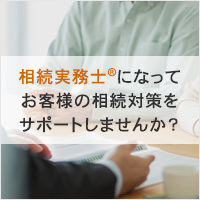事例
相続実務士が対応した実例をご紹介!
相続実務士実例Report
83歳まで借入返済して達成感をという税理士!?対策の発想はない!

■両親と同居する跡継ぎ
Uさん(60代女性)から相談がありました。Uさんの父親は300坪の土地を持つ資産家。昭和40年代から貸家を建てて賃貸事業をしてこられました。Uさんは3姉妹の長女で、幼いころから家の跡継ぎになるようにと言われて育ってきました。
妹たち二人もそれに異論はなく、2人とも嫁いで家をはなれています。
Uさんも結婚して父親の持つ敷地内に家を建てて同居生活を始めました。2人の子どもに恵まれましたが、夫と両親の折り合いが悪く、子どもたちが小学校に入る前に離婚。当然、子ども2人はUさんが育てたと言います。
結果、Uさんは一度も実家を離れることなく、両親と同居して、両親を看取ってきたのです。
■土地を生かして賃貸事業
最寄駅から徒歩10分の閑静な住宅地にある土地です。父親の始めた賃貸事業は母親も一緒に運営して、家賃を集金に行ったり、好調でしたが、築年数が経ち、空き家も出てきたため、Uさんが中心になって計画し、父親の相続税の節税対策として敷地の6割ほどに3階建てRC造の賃貸マンションを建てることにしました。
事業費1億7000万円を銀行から借り入れ、1R~1LDK13世帯の賃貸マンションが出来上がり、新たな賃貸事業がスタートしました。
■父親の相続税はかからず、賃貸事業も成功
マンションを建ててから数年して父親が亡くなりましたが、借入のマイナスが効果的で、相続税はかかりませんでした。父親の相続の時に自宅と賃貸マンションの土地、建物は母親ではなく、Uさん名義にしましたので、いよいよUさんの賃貸事業となったのです。
賃貸事業の収支は下記のとおりで、相続税を節税しながら、家賃収入を得ることができ、借入返済と固定資産税、所得税などの納税後の手取りは家賃の30%以上の年間600万円程あります。賃貸事業も成功していると言えます。
■一人暮らしになって10年近く
Uさんの両親が亡くなり、2人の娘たちは嫁いで別世帯ですので、300坪の土地にUさんは一人暮らしです。コロナの期間もあり、子どもたちにも頼れず、ひとりで賃貸事業を継続してきました。賃貸マンションは入れ替わりはあるにしても、ほとんど満室。そのためにバーベキュー大会をしたり、餅つき大会をしたりと入居者ともほどよいコミュニケーションを取ってきたといいます。空室になったときのリフォームも両親がそうしてきたように全部自分で手配しています。それだけにずっとかかりきり。旅行などで長期の不在にしてはいけないという意識で、賃貸業に徹してきたのでした。
けれどもUさんも60代の後半になり、体調が思わしくないときもあり、このペースで継続していくことにつかれてきたと言います。そうしたことを娘に話すと「自宅とマンション、全部売って楽になったほうがいい」と言われたのです。
■税理士は83歳まで返済しろという
Uさんは自分が父親から相続したように、いずれ、娘たちに引き継いでもらおうと
考えていましたが、娘の言葉を聞いてはっとしたと言います。そうした選択肢もあると思い、毎年の確定申告を依頼している顧問税理士にも相談してみたのです。
税理士のアドバイスは、「借入を完済して達成感を味わったらどうですか」と。借入を返済するまであと13年。Uさんは83歳になります。
こうしたいきさつがあり、どうすればいいかというのがUさんのご相談内容でした。Uさんは「自分の人生、これでいいのだろうかという疑問が出てきた」とも言われました。
■財産は状況に合わせて持ち変えるべき!
賃貸事業の収支は悪くないので、借入返済がある間の13年、維持することはできると言えますが、それには常に満室にする努力が必要です。修繕費やリフォーム代も必要になるため、今まで以上に力をいれないといけない状況になります。借入返済後は手取りもよくなりますが、築35年の賃貸マンションを維持するための方策があれこれ必要になり、これも簡単ではありません。
70代、80代で、いままでどおりに日々、賃貸事業に携わることは大変だと言えます。
よってUさんの人生を考えるのであれば、現在の不動産を手放し、借入も返済し、子どもたちと行き来しやすい立地に住みかえ、手間のかからない築浅の賃貸物件に持ち変えることのほうが現実的だとお勧めしました。
顧問税理士が「83歳まで現状維持、借入返済した達成感を得てもらいたい」というアドバイスは、Uさんと子どもたちの心情に寄り添っているとは思えません。財産のために人生を犠牲にすることはナンセンスだといえます。
それよりも、財産を生かしてUさんと子どもたちが将来的にも不安がなく、楽しみが持てる人生を選択してもらいたいという思いです。
Uさんは売却して住み替えの方向で子どもたちにも話をして、決断していきたいと言われました。どのタイミングにするか、決めるということです。
■参考 賃貸事業の収支など検証)
◇前提条件
- 建設費(借入額):1億7,000万円(全額借入)
- 借入期間:35年(元利均等返済)
- 金利:1.5%
- 家賃収入(年額):1,800万円
◇① 年間ローン返済額(元利均等方式)
元利均等返済では、年利1.5%、期間35年(=420ヶ月)の場合、年返済額は以下のように求められます。
年間返済額の計算(概算)
借入額:1億7,000万円
金利:1.5%
期間:35年
▼ローン返済シミュレーションを使った概算結果:
- 年間返済額:約 602万円
◇② 年間キャッシュフロー
- 家賃収入:1,800万円
- ローン返済額:▲602万円
- その他経費(管理費・修繕・空室損等):
一般的に家賃収入の20〜30%程度とされます。ここでは25%で試算。
経費=1,800万円 × 25% = 450万円
◇③ 年間手取り(税引前)
手取り=家賃収入−経費−ローン返済=1,800万円−450万円−602万円=∗∗748万円∗∗手取り = 家賃収入 − 経費 − ローン返済 = 1,800万円 − 450万円 − 602万円 = **748万円**
◇④ 家賃収入に対する割合
- ローン返済の割合:602万円 ÷ 1,800万円 = 33.4%
- 経費の割合:450万円 ÷ 1,800万円 = 25.0%
- 手取り割合:748万円 ÷ 1,800万円 = 41.6%
◇まとめ表
|
項目 |
金額(万円) |
割合 |
|
家賃収入 |
1,800 |
100% |
|
経費(25%) |
▲450 |
25.0% |
|
ローン返済 |
▲602 |
33.4% |
|
手取り(税引前) |
748 |
41.6% |
◇ ポイント
- 税引後のキャッシュフローは 年間約635〜650万円前後で安定。
- 借入残高は毎年約3.5〜4百万円ずつ減少。
- 減価償却による「帳簿上の赤字」は税額を軽減し、キャッシュが残る構造。
■参考 【1】持ち続ける vs 【2】売却して買い替える
現状の財産を持ち続けた場合と、買い替えた場合、2つの選択肢について、メリット・デメリットを整理します。
【1】持ち続ける場合
- メリット
|
項目 |
内容 |
|
安定収入の維持 |
年間家賃収入1,800万円を継続的に確保可能(管理費・税引後も年間手取り600万円以上見込み) |
|
減価償却メリット継続 |
残存簿価次第で、引き続き減価償却による節税が可能(特に残存期間中の節税効果) |
|
ローン残債の減少 |
元本返済で純資産(エクイティ)が増加する=将来の売却益がさらに大きくなる |
|
資産の保有 |
土地・建物はインフレヘッジ資産として保有価値がある |
- デメリット
|
項目 |
内容 |
|
建物の老朽化リスク |
修繕費・設備更新費が増える(大規模修繕の発生リスクも高い) |
|
空室リスク |
築年数が進むほど空室リスク・賃料下落の可能性が高まる |
|
減価償却の終了間近 |
節税効果が縮小していく(RC造の場合、耐用年数47年のため22年経過時点で残償却期間は約25年) |
|
売却タイミングを逸する |
今後、金利上昇・需給悪化で売却価格が下がるリスクも |
■【2】売却して買い替える場合
- メリット
|
項目 |
内容 |
|
売却益(キャッシュ)確保 |
売却額2億2,500万円 − ローン8,000万円 = 約1億4,500万円の現金確保 |
|
資産の組み替え可能 |
築浅・収益性の高い物件に買い替えることで、減価償却を再スタートでき節税効果も回復 |
|
修繕・空室リスクの回避 |
老朽物件を手放すことで、今後の大規模修繕や入居率低下リスクを回避可能 |
|
相続対策に活用可能 |
売却→借入付き物件に再投資することで評価減+収益確保が可能(0円相続にも応用可) |
- デメリット
|
項目 |
内容 |
|
譲渡所得課税が発生 |
長期譲渡でも約20%の譲渡所得税が発生(取得価格・簿価によるが数千万円単位の納税も) |
|
買い替えの目利きが必要 |
新規取得物件の利回り・立地・運用管理力などの見極めが重要(失敗リスクあり) |
|
一時的に収入が止まる可能性 |
売却から新規運用までの空白期間に収入が途切れるリスク |
◇判断のポイント(中立的な提案)
|
条件 |
持ち続ける |
売却して買い替える |
|
税金の繰延べ重視 |
◎ 減価償却で節税可能 |
△ 譲渡益課税が発生 |
|
修繕・空室の不安あり |
△ リスク増大 |
◎ 築浅化・空室リスク回避 |
|
今の管理が良好 |
◎ 継続運用で安心 |
△ 新規物件の見極め必要 |
|
相続対策も視野に |
△ 評価が高止まりする可能性 |
◎ 借入付きで組み替え効果大 |
■結論
相続を意識するなら:いまの売却益を活かして「借入を伴う築浅物件」などに買い替え → 評価圧縮+減価償却による節税で「収入・相続対策」を両立
リスクを抑えたいなら:手堅く「持ち続け」+「数年後売却」でも選択肢としてOK。ただし修繕費の増加と家賃下落が想定され、売却価格は減少する
よって、早めの売却、住みかえ、買い替えが妥当だと言えます。
最初のご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください → 【ご相談受付・詳細のご案内】
コラム執筆